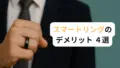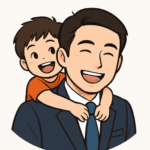
こんにちは。出張パパと申します。
2025年6月の生成AIパスポート試験を合格することができました。
「今話題の生成AIパスポート試験、受けてみたいけど難易度はどれくらい?」「どうやって勉強すればいいの?」 これから受験を考えている方は、こんな疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、実際に試験について調査・受験した筆者が、生成AIパスポートの難易度・合格率から、最短で合格するための具体的な勉強法までを徹底解説します。
結論から言うと、生成AIパスポートは適切な対策をすればAI初心者でも十分に合格可能な資格です。この記事を読めば、合格までのロードマップが明確になります。
1. 「生成AIパスポート」とは?

「生成AIパスポート」は、2024年に新設された注目の民間資格です。
AIの基礎知識からChatGPTなどの生成AI活用、プロンプト設計、法的リスクや倫理まで網羅しています。
- 対象者:ビジネスパーソン、学生、教育関係者、IT非専門職など
- 目的:生成AIの正しい活用とリテラシー向上
- 証明:合格者には認定証とオープンバッジを発行
最近では、三菱商事をはじめとする企業がAI資格を昇格要件に含めるなど、需要が高まっています。
2. 生成AIパスポートの難易度と合格率は?
合格率は約70%前後
直近の試験データによると、合格率は概ね**70%〜75%**程度で推移しています。2025年6月の合格率は77.14%でした。
難易度は「易しい〜普通」
ITパスポート試験などと比較しても、極端に難しい試験ではありません。エンジニアなどの専門職でなくても、ビジネスパーソンや学生でも理解できる内容が中心です。ただし、「著作権」や「個人情報保護法」などの法律周りは引っ掛け問題も多いため、油断は禁物です。
合格率は決して低くなく、初学者でもしっかり対策すれば合格可能な試験と言われています。
私の学習期間は約1週間で、1日3時間×5日程度の勉強量でした。
試験問題の多くは公式シラバスから出題されており、公式シラバスを2〜3周できれば、問題なく合格できるかと思います。
2025年6月試験についても、個人的な感覚ですが、約8割は公式シラバスで対応できる内容だったと思います。
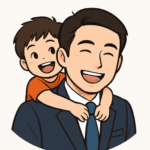
この分野は進歩が著しく、年々試験が難化されることを予想しています。
興味があるのであれば、早めの受験を考えてみることをおすすめします。
ちなみに、2025年6月の受験者数は過去最多の1万759人に上り、8300人が合格しています。
累計では受験者数が2万7101人、有資格者数は2万900人とのことです。
3. 試験概要とスケジュール
試験概要について、ざっくりまとめてみました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験形式 | 四択60問/60分/オンライン受験(IBT形式) |
| 出題範囲 | AI基礎、生成AI、活用事例、情報リテラシー、プロンプト設計など |
| 受験料 | 一般:11,000円(税込)/学生:5,500円(税込) |
| 実施回数 | 年3回(2月・6月・10月)※1ヶ月の受験期間あり |
| 合格基準 | 非公開(合格率75〜77%程度) |
| 合格証明 | 認定証・オープンバッジ(SNSや履歴書に活用可能) |
試験は期間内の好きな時間に受けることができます。
例えば10月試験であれば、10月1日〜30日までの間であれば、自分が好きな時間帯に受験することができます。
またオンライン受験のため、自宅で受けることもできます。
自分のタイミングと受験場所を指定することができるので受験しやすいこともポイントが高いです。
ネックなのは受験料が比較的高いことです。
費用対効果はあると思いますが、一発合格できるようにしっかり準備をしておきましょう。
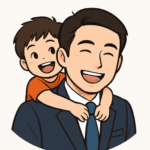
合格基準は公開されていません。
出張パパの正答率は約90%でした。
ネットで検索すると、8割程度が合格ラインでは?と言われています。
出張パパは、自宅で子供が寝た後の深夜帯に受験しました。
4. 出題範囲の詳細(章構成)

出題内容は、公式シラバスをもとに出題されます。
最新の公式シラバス(2025年3月20日第二刷)は7つの大項目で構成されていました。
【第一章】AIの概要:AIとは、AItoロボットの相違、AIの出発点と現在
【第二章】生成モデルの誕生と現在までの系譜:生成モデルの誕生、生成モデルと系譜と技術の基礎
【第三章】現在の生成AIの動向:各種の生成AIの特徴、各種の生成AIのメリット・デメリット、ディープフェイクの特徴
【第四章】インターネットセキュリティーと権利関係:インターネットリテラシーとは、セキュリティとプライパシー保護
【第五章】AIに関する基本理念・社会原則・ガイドライン:AIの利活用に関するルール、人間中心のAI社会原則の基本理念
【第六章】テキスト生成AIに関するプロンプト:プロンプトとは、LMの概要、LMMの概要
【第七章】生成AIパスポート試験模擬問題
実際にChatGPTなどの生成AIを日頃から使用している人でも、聞きなれない単語や法律などの知識が問われるため、ある程度の勉強期間が必要になってきます。
5. 生成AIパスポート試験 勉強法とおすすめ教材【合格体験記】
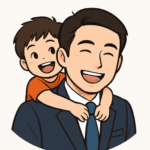
実際に私が試した学習法は以下のとおりです。
公式テキストは2種類あるのですが、公式テキスト&問題集を使用しました。
- ✅ Kindleで漫画風書籍を2冊:一旦漫画風の書籍で感覚を養う。
- ✅ 公式テキストを2周:繰り返しが効果的。暗記勝負の内容が多い。
- ✅ Kindleで直前問題集を1冊:テスト形式で最終復習してそのまま試験へ。
まず漫画風であればとっかかりやすいかと思い、Kindle Anlimitedで読める生成AIパスポート関連の書籍を探し、以下の2冊を読みことから始めました。
- ✅ はじめての生成AIパスポート:マンガでわかる!
- ✅ 生成AIパスポートの教科書:忙しい人のための超解釈本(2025年5月改定版)
ある程度流れを覚えらたら、公式テキストを進めました。
試験問題の多くは公式シラバスから出題されており、公式シラバスを2〜3周できれば、問題なく合格できるかと思います。
2025年6月試験についても、個人的な感覚ですが、約8割は公式シラバスで対応できる内容だったと思います。
特別なITスキルは不要ですが、日頃から生成AIに触れている方ほど学習時間は短くて済むかと思います。
最後に、2025年版AIパスポート試験対策一問一答(50選)で問題を解き、そのまま試験を受けました。
試験は期間内であれば、いつでも自分も好きな時間に受けることができます。
公式テキストの注意したい点としては、必ずテキストは最新版で勉強する必要があるという点です。
主催者も、年々テキストの内容が変更される可能性があることをお知らせしています。
下記テキストは、2025年7月時点で最新版であることを確認しているので、チェックしてみてください。
6. 資格を取得するメリット

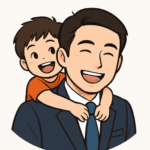
生成AIパスポートを取得することで、以下のようなメリットを実感しています。
① 「AIを使える」証明になる
履歴書やプロフィールに記載することで、AIリテラシーがあることを客観的に証明できます。
表記方法については、下記のように履歴書に記載できるそうです。
【例1】
GUGA 生成AIパスポート 2025年2月 資格取得
GUGA Generative AI Passport, Feb 2025 Certified
【例2】
生成AIパスポート 2025年2月 資格取得
Generative AI Passport, Feb 2025 Certified
② リスク回避能力がつく
企業でAIを導入する際、最も懸念される「著作権侵害」や「情報漏洩」のライン引きができるようになります。
③ 昇進・転職・社内提案で差別化できる
社内のDX推進や業務改善の提案に説得力が増し、昇進や異動のチャンスが広がります。
実際に、一部企業では生成AI資格を昇格要件に含め始めています。
「生成AI活用できる人材=即戦力」として評価されやすくなるのは大きな利点です。
④ 最新トレンドに強くなる
資格取得を目指す過程で、自然と生成AIそのものに対する興味が深まります。
実際、私自身も資格取得後、GUGAから届く生成AI関連イベントの案内メールに目が止まり、参加するようになりました。
また日常的に出会うAI関連のニュースの意味が深く理解できるようになります。
7. 生成AIパスポートがおすすめな人/おすすめでない人
生成AIパスポートは、比較的短期間で取得できるうえ、実務に直結する知識が得られる資格です。
こんな方に特におすすめです。
- 業務で生成AIをすでに使っている、またはこれから使う予定がある人
- AIの基礎から法的リスク・倫理まで幅広く体系的に学びたい人
- DX推進や社内教育を担当している人
- 履歴書やプロフィールにAI資格を載せて、信頼性を高めたい人
逆に、以下のような方にはあまり向きません。
- AIやIT分野に全く興味がない人
- 資格取得をキャリアや業務に活かす意欲がない人
- 受験料や学習時間を確保できない人(受験料は一般11,000円)
資格はあくまで「活用してこそ価値が出る」ものです。
取得後にどう活かすかをイメージしておくと、学習モチベーションも高く保つことができます。
8. まとめ:生成AIパスポートは最初のステップにおすすめ
生成AIパスポートは、これからのAI時代を生きていくための「基礎免許」のような資格です。難易度はそこまで高くありませんが、学ぶ内容は実務で非常に役立ちます。
今回紹介したように、この資格は
- 初学者でも1〜2週間の集中学習で合格可能
- 合格率は約75〜77%と比較的高い
- 履歴書やプロフィールでスキルをアピールできる
という特徴があります。
「そのうち受けよう」と考えている間にも、AI技術と試験内容は進化していきます。
早めに合格しておくことで、変化の激しいAI分野で一歩リードできます。
ぜひ次回試験の日程をカレンダーに入れて、今日から学習を始めてみてください。
未来のキャリアを広げる第一歩は、行動することからです。